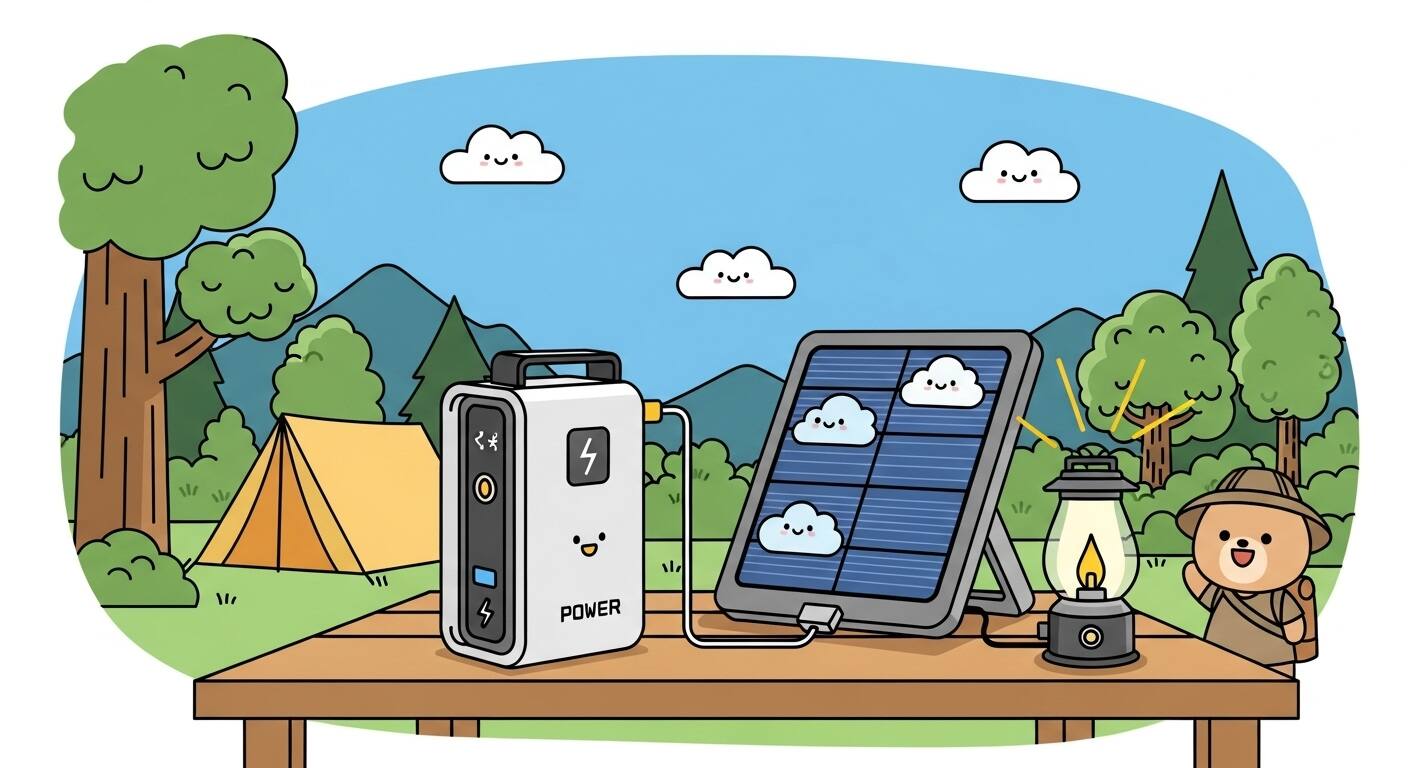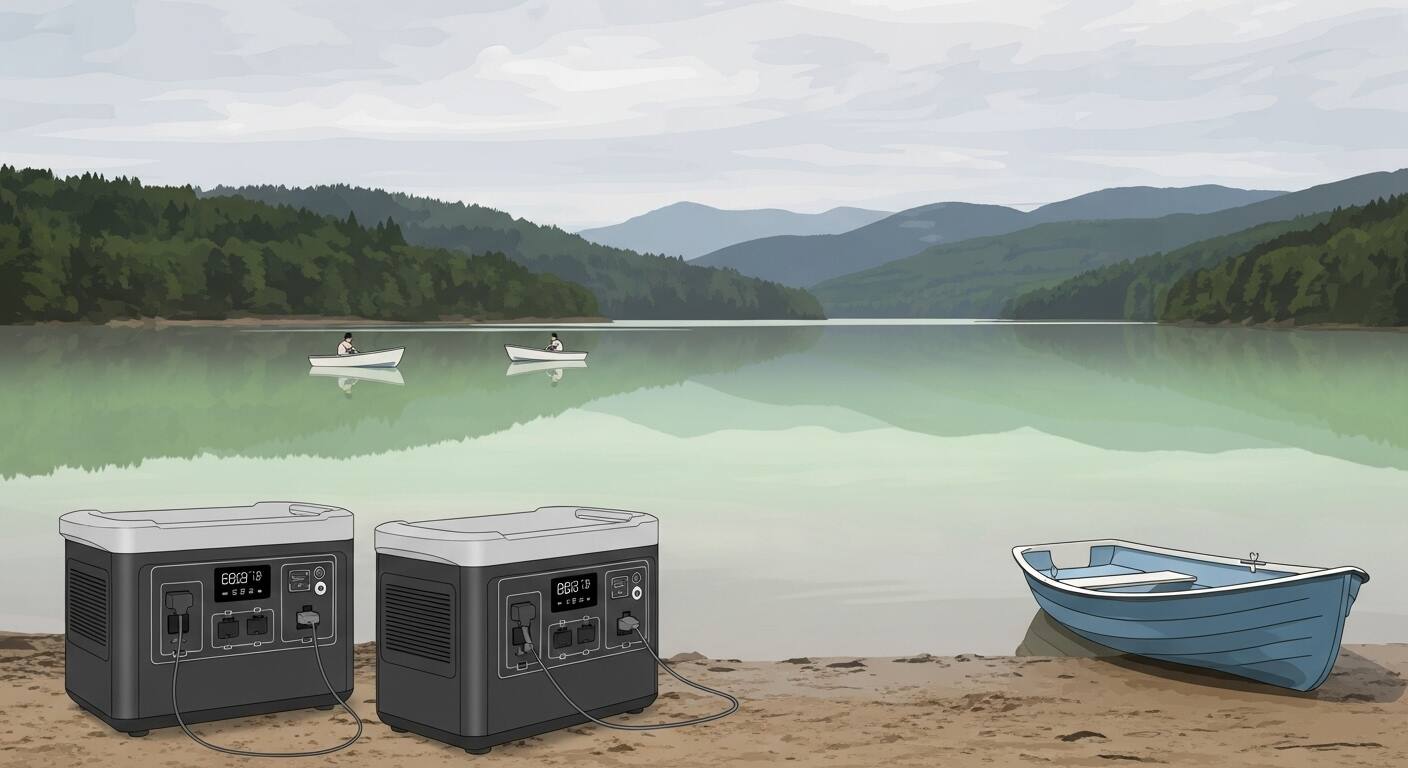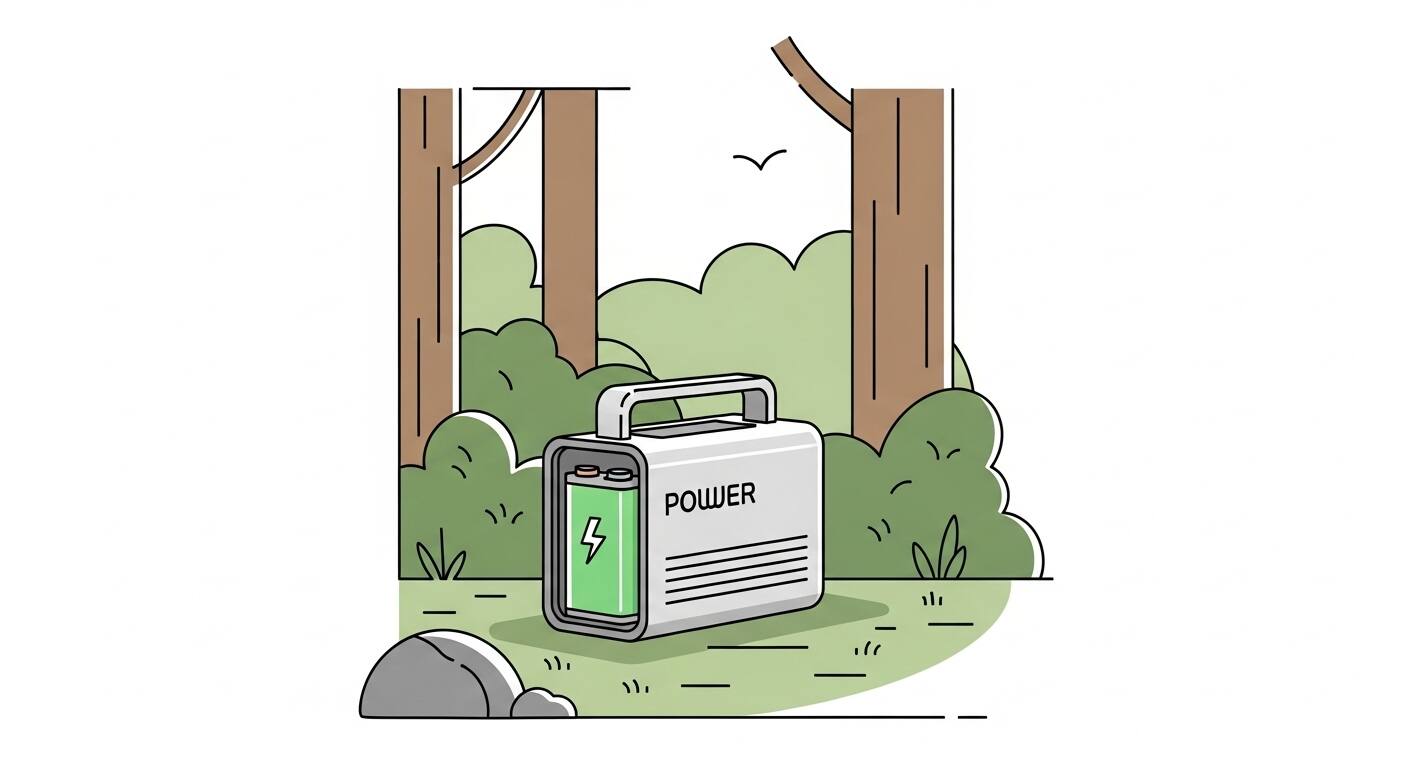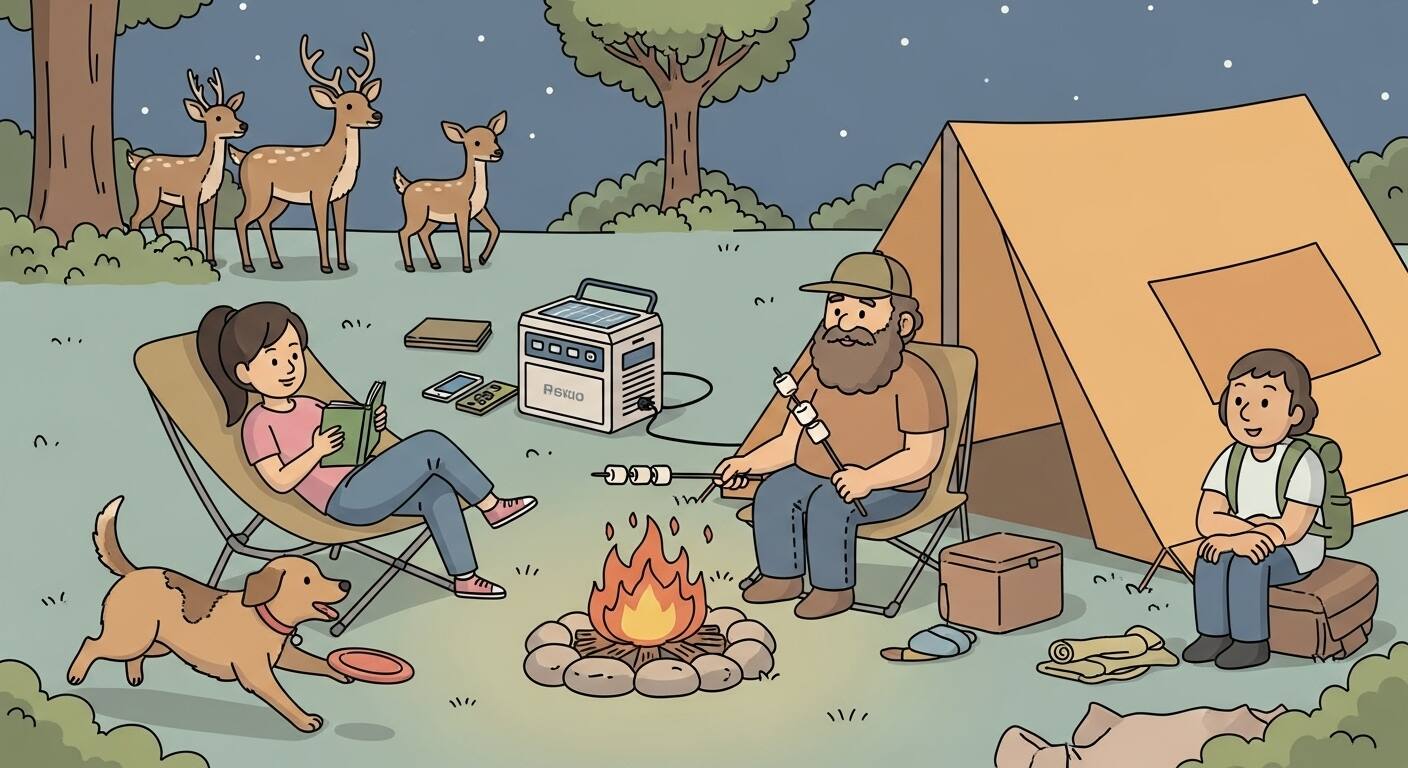ポータブル電源のパススルーは寿命を縮める?その真実と後悔しない選び方を徹底解説

PR
ポータブル電源選びで、多くの人が気になる「パススルー充電」機能。コンセントに繋いだまま機器を使えるなんて、最高に便利そうですよね。でも、その一方で「パススルーはバッテリーの寿命を縮める」なんて怖い噂も耳にしませんか?「便利さを取るか、寿命を取るか…」なんて、究極の選択を迫られている気分になっている人もいるかもしれません。
結論からお伝えします。パススルー機能は、使い方と製品選びを間違えなければ、ポータブル電源の寿命を極端に縮めることはありません。むしろ、最新モデルでは寿命への影響を最小限に抑える技術が搭載されており、正しく理解すればこれほど心強い機能はないのです。この記事を読めば、パススルー機能の本当の実力と、あなたの使い方に最適な一台を見つけるための知識が身につきます。
もう、漠然とした不安に悩まされることはありません。キャンプや防災、日常使いでポータブル電源を最大限に活用し、長く愛用するための具体的な方法を、余すところなくお伝えします。
パススルー機能がポータブル電源の寿命を縮めると言われる本当の理由
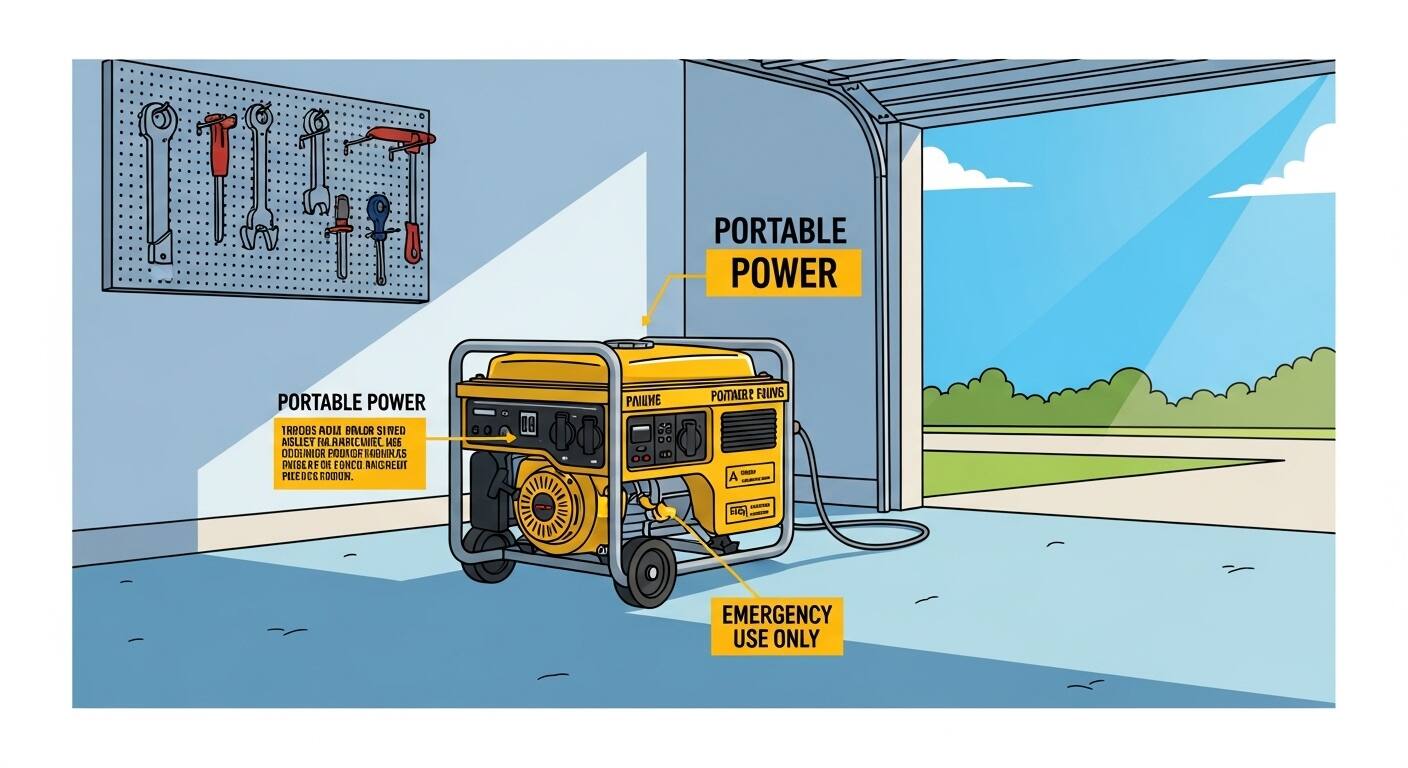
多くの人が「パススルー=寿命が縮む」と心配するのには、ちゃんとした理由があります。ただ、それは少し昔の話になりつつあるかもしれません。なぜそう言われるのか、そのメカニズムと、最近の技術がどうやってその問題を克服しようとしているのか。まずは、この核心部分からじっくりと解き明かしていきましょう。ここを理解するだけで、ポータブル電源選びの解像度がグッと上がるはずです。
そもそもパススルー充電ってどんな仕組み?
「パススルー」って、言葉だけ聞くと何だか難しそうに感じますよね。でも、やってることは意外とシンプルなんです。一言でいうと、「ポータブル電源を充電しながら、同時に他の機器にも給電する機能」のことです。
イメージしてみてください。壁のコンセントからポータブル電源に充電ケーブルを繋ぎます。そして、そのポータブル電源のACコンセントやUSBポートに、今度はスマホやノートパソコンを繋ぐ。この状態で、ポータブル電源本体の充電と、スマホやパソコンへの給電が同時に行われる。これがパススルーです。まるで、コンセントの数を拡張してくれる魔法の箱みたいですよね。
この仕組み、実は2種類あるんです。一つは「バッテリー経由型」。これは、壁のコンセントからの電気が一度すべてポータブル電源のバッテリーに蓄えられ、そこからスマホなどに給電される方式です。電気の流れが「コンセント→バッテリー→接続機器」となるわけです。初期のモデルや安価なモデルの多くがこのタイプでした。
もう一つが、最近の高性能モデルに増えてきた「バイパス型(UPSモードとも呼ばれる)」。こちらは、壁のコンセントからの電気を、バッテリーを介さずに直接スマホなどの接続機器へ流すことができます。そして、余った電力や、給電に使われていない時にバッテリーを充電する。電気の流れが「コンセント→接続機器」と「コンセント→バッテリー」の二手に分かれるイメージです。これが、後で話す「寿命」の問題を解決する大きなカギになるんですよね。
「熱」と「充放電」こそがバッテリー寿命の天敵
では、本題です。なぜパススルー、特に先ほどの「バッテリー経由型」が寿命を縮めると言われるのか。犯人は、ずばり「熱」と「絶え間ない充放電」です。この二つは、リチウムイオンバッテリーにとって最大の敵と言っても過言ではありません。
まず「熱」。バッテリーは化学反応で電気を蓄えたり放出したりするのですが、充電中も放電中も、内部では熱が発生します。パススルー中は、充電による熱と放電による熱が同時に発生することになる。もう、バッテリーからしたら「勘弁してくれ!」って状態ですよね。サウナに入りながら全力疾走させられているようなものです。リチウムイオンバッテリーは高温に非常に弱く、熱によるダメージはバッテリー内部の素材をジワジワと劣化させ、蓄えられる電気の量を減らしていきます。これが「寿命が縮む」という現象の正体です。
次に「絶え間ない充放電」。バッテリー経由型の場合、ポータブル電源に繋いだ機器が電気を使うと、バッテリー残量はわずかに減ります。すると、すかさず充電が始まり、100%に戻そうとします。そしてまた少し電気が使われると、また充電が始まる…。この細かな充放電が延々と繰り返されるわけです。バッテリーの寿命の目安として「サイクル回数」という指標がありますが、この細かい繰り返しも、確実にサイクル回数を消費し、バッテリーを疲弊させていく原因になるのです。まるで、満タンのバケツからコップ一杯の水を汲み、すぐに水道で満タンまで補充する作業を永遠に繰り返しているようなもの。地味ですが、確実にダメージは蓄積されていきます。
ポータブル電源のパススルー機能と賢く付き合い寿命を延ばす方法
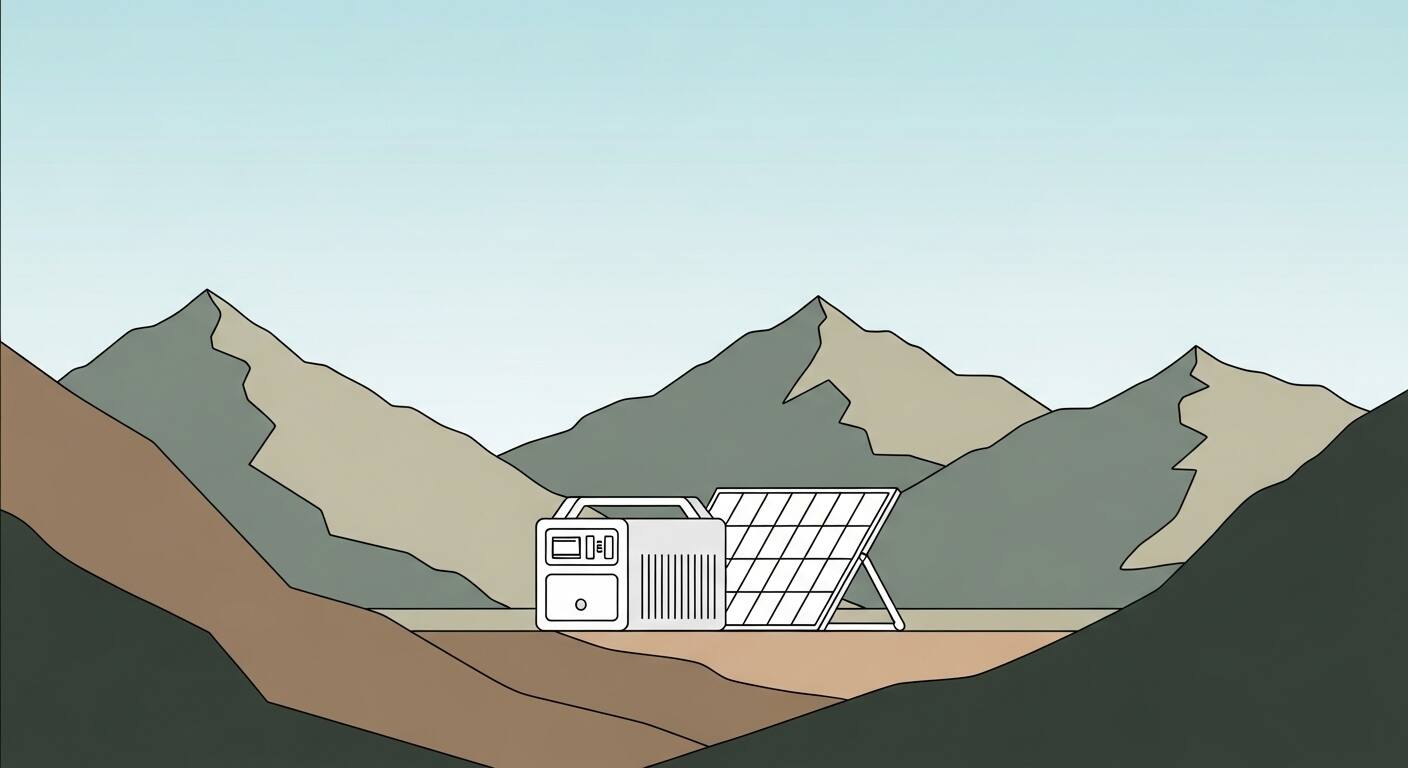
パススルーが寿命に影響を与える可能性があるのは事実です。でも、だからといって「パススルー機能は絶対に使わない方がいい!」と結論づけるのは早計すぎます。現代の技術と少しの工夫で、そのリスクは大幅に軽減できるんです。ここでは、お持ちの、あるいはこれから手に入れるポータブル電源と、どうすれば長く良い関係を築けるのか、具体的な付き合い方についてお話しします。
常時接続は避けるべき?パススルーの上手な活用シーン
「じゃあ、パススルーはどんな時に使えばいいの?」って思いますよね。ぶっちゃけ、毎日24時間、冷蔵庫のように常時接続してパススルーを使い続けるのは、あまりおすすめできません。特に、先ほど説明した「バッテリー経由型」のモデルの場合はなおさらです。
では、どんなシーンなら輝くのか。例えば、キャンプや車中泊のシーン。日中にソーラーパネルでポータブル電源を充電しながら、同時にスマホや扇風機を使う。これは非常に賢い使い方です。常に充電し続けているわけではなく、一時的な利用なのでバッテリーへの負荷も限定的です。
また、停電対策としての「簡易的なUPS(無停電電源装置)」としての利用も素晴らしい活用法です。デスクトップパソコンや、録画中のレコーダーなど、一瞬でも電源が落ちると困る機器を繋いでおく。普段は「バイパス型」でバッテリーを介さずに電力を供給し、万が一停電した瞬間にバッテリーからの給電に切り替わる。これなら、バッテリーに負荷をかけるのは停電した時だけです。
ただし、このUPS機能は、全てのパススルー対応機種に備わっているわけではありません。特に切り替え時間の速さが重要で、これが遅いとパソコンなどは再起動してしまいます。製品の仕様書で「UPS機能搭載」や「切り替え時間20ms(ミリ秒)以下」といった表記があるかを確認することが重要です。
最重要!ポータブル電源の「冷却」を意識した使い方
バッテリーの天敵は「熱」である、という話をしました。ということは、答えはシンプル。徹底的に冷やしてあげればいいんです。え?氷で冷やすとかそういう話じゃないですよ。もっと簡単で、誰にでもできる工夫の話です。
まず、置き場所。これが一番大事かもしれません。ポータブル電源をどこに置いていますか?まさか、直射日光がガンガン当たる窓際や、熱がこもりやすい車のダッシュボードの上、なんてことはないですよね。夏場の車内なんて、目玉焼きが焼けるほどの高温になります。そんな環境は、バッテリーの寿命をものすごい勢いで削り取っていきます。風通しの良い、日陰の涼しい場所に置いてあげる。これだけで、バッテリーの寿命は大きく変わってきます。
次に、ファンの働きを邪魔しないこと。ポータブル電源は、内部が熱くなると冷却ファンが「ウィーン」と回り始めます。これは「今、頑張って冷やしてるよ!」というサインです。この時、吸気口や排気口を壁にぴったりつけたり、布で覆ったりしてしまうと、熱が内部にこもってしまいます。人間が、真夏にダウンジャケットを着せられているような状態です。本体の周りには、最低でも15cm以上のスペースを空けて、空気の通り道を確保してあげましょう。当たり前のようで、意外とできていないことが多いポイントです。
究極の解決策「バイパス型パススルー」搭載モデルを選ぶ
いろいろと工夫について話してきましたが、「もう、ごちゃごちゃ考えたくない!」「安心してパススルーを使いたい!」という人も多いでしょう。うん、わかります。その気持ち。そんなあなたにとっての究極の解決策は、もうこれしかありません。「バイパス型のパススルー機能を搭載したモデルを選ぶこと」です。
先ほども少し触れましたが、バイパス型は、ACコンセントからの電力をバッテリーを通さず、直接接続機器に流します。この時、バッテリーは充電も放電もしていない、いわば「お休みモード」に入っています。熱の発生源である充放電が行われないので、バッテリーへの負荷が劇的に少ないのです。これなら、簡易的なUPSとして常時接続しておく使い方をしても、バッテリーの劣化を最小限に抑えられます。
もちろん、停電などで壁のコンセントからの電力供給が途絶えれば、瞬時にバッテリーからの給電に切り替わります。この賢い仕組みのおかげで、「普段の利便性」と「バッテリーの長寿命」という、二律背反に思えたテーマを両立できるわけです。最近のミドルクラス以上のモデル、特にUPS機能を謳っている製品の多くがこのバイパス方式を採用しています。もし、パススルー機能を頻繁に使うことが想定されるなら、ここは絶対に妥協してはいけないポイント。初期投資は少し高くなるかもしれませんが、長い目で見れば、バッテリー交換のコストや買い替えの手間を考えれば、むしろ経済的だと言えるかもしれません。
【主要メーカー比較】パススルー機能と寿命で選ぶポータブル電源

じゃあ、具体的にどのメーカーのどのモデルがパススルーに強いのか。気になりますよね。ここでは、主要なメーカーである「EcoFlow」「Anker」「Jackery」「BLUETTI」の4社に絞って、それぞれのパススルー機能の特徴や、寿命に対する考え方を見ていきたいと思います。あくまで第三者的な視点での評価であり、特定の製品を推奨するものではありませんが、あなたの製品選びの助けになるはずです。
充電速度と機能性の「EcoFlow(エコフロー)」
EcoFlow社といえば、なんといっても業界をリードする圧倒的な充電速度「X-Stream」技術が有名です。この技術は、パススルー時にもその真価を発揮します。大容量モデルであっても短時間で充電が完了するため、バッテリーが高温に晒される時間が短くて済む、というメリットがあります。
同社のDELTAシリーズやRIVERシリーズの多くは、EPS(Emergency Power Supply)と呼ばれる簡易UPS機能を搭載しています。これはバイパス型に近く、ACからの電力を優先的に出力側に流し、停電時には約30ms(0.03秒)という速さでバッテリー給電に切り替わります。デスクトップPCのような精密機器でも、ほとんどの場合、問題なく使い続けられるレベルです。
ただし、完璧なオンラインUPSとは異なるため、サーバーのような絶対に電源断が許されない機器への使用はメーカーも推奨していません。とはいえ、家庭での利用においては十分すぎる性能と言えるでしょう。パススルーを使いながら、独自の「X-Boost」機能で定格以上の消費電力の家電を動かせるなど、機能性の高さも魅力です。
安心感と高性能を両立する「Anker(アンカー)」
モバイルバッテリーや充電器で絶大な信頼を誇るAnker。その技術力を結集したポータブル電源「Anker Solix」シリーズ(旧PowerHouseシリーズ)もまた、非常に高い評価を得ています。Anker製品の強みは、なんといってもその安全性と信頼性。パススルー機能においても、その哲学は貫かれています。
Ankerの多くのモデルでは、20ms(0.02秒)未満の高速切り替えが可能なUPSレベルのパススルー機能を搭載しています。これは業界でもトップクラスの速さです。特筆すべきは、コンセントに挿しっぱなしで利用する「常時充電モード」を公式にサポートしている点。内蔵バッテリーを保護しながら、満充電状態を維持する制御がされており、ユーザーが安心してUPSとして使えるように設計されています。また、多くのモデルで長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、パススルー利用時の安心感は非常に高いと言えます。手厚いカスタマーサポートと長期保証も、Ankerを選ぶ大きな理由の一つでしょう。
パイオニアとしての信頼と実績「Jackery(ジャクリ)」
ポータブル電源のパイオニア的存在であるJackery。オレンジ色のボディは、アウトドア好きなら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。Jackery製品は、そのシンプルで直感的な使いやすさと、高い安全性で定評があります。
パススルー機能に関しては、Jackeryも多くのモデルで対応しています。ただし、同社は「バッテリーの寿命を最優先に考える」という姿勢を明確にしています。そのため、公式サイトなどでは、パススルー充電はバッテリー寿命に影響を与える可能性があるため、頻繁な使用や長時間の使用は推奨しない、という旨のアナウンスがされています。これは、ユーザーに対して非常に誠実な態度と言えるでしょう。UPS機能として積極的に謳っているモデルは他社に比べて少ないですが、これは性能が低いというよりは、メーカーとしての哲学の違いと捉えるべきです。キャンプなどで一時的にパススルーを使う、といった用途であれば、Jackeryの信頼性は大きなアドバンテージになります。
長寿命バッテリーの先駆者「BLUETTI(ブルーティ)」
BLUETTIは、いち早くリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリーを多くのモデルに採用し、「長寿命」という価値をポータブル電源市場に根付かせたメーカーです。サイクル寿命が3,500回以上といった、他を圧倒するスペックのモデルを数多くラインナップしています。
パススルー機能に関しても非常に高性能で、多くのモデルで高速なUPS機能を搭載。特筆すべきは、AC300やAC500といった超大容量モデルに見られる「オンラインUPS」機能です。これは、常にバッテリーを介して安定した電力を供給する方式で、停電時の切り替え時間がゼロという、まさに業務レベルの性能を誇ります。もちろん、この方式はバッテリーへの負荷が大きくなりますが、それをものともしない長寿命バッテリーを搭載しているからこそ実現できる機能と言えます。パススルー機能をヘビーに使いたい、そして何よりも長く使い続けたい、というニーズに対して、BLUETTIは非常に強力な選択肢となるでしょう。
まだある!ポータブル電源の寿命を左右するパススルー以外の重要ファクター

パススルー機能のことばかり気になってしまいますが、ポータブル電源の寿命を決める要素は、実はそれだけではありません。むしろ、これからお話しすることの方が、日々の使い方においては重要かもしれません。バッテリーの種類、保管方法、そして充放電の仕方。この3つのポイントを押さえることで、あなたのポータブル電源はもっと長く、元気に活躍してくれるはずです。
心臓部!バッテリーの種類「リン酸鉄」か「三元系」か
ポータブル電源の心臓部であるバッテリー。現在主流なのは「リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP)」と「三元系リチウムイオン電池(NCM/NCA)」の2種類です。この違いは、寿命を考える上で決定的に重要です。
まず、最近のトレンドである「リン酸鉄リチウムイオン電池」。こいつの最大のウリは、なんといっても「長寿命」と「安全性」です。充放電を繰り返せる回数の目安であるサイクル寿命が、一般的に2,000回から4,000回と非常に長い。毎日使っても10年近く持つ計算になるモデルもあるくらいです。え、凄すぎません?また、熱暴走のリスクが低く、安全性が高いのも大きなメリット。デメリットは、エネルギー密度が三元系に比べて少し低いため、同じ容量だと少し重く、大きくなりがちなことと、コストがやや高めな点です。
一方の「三元系リチウムイオン電池」。こちらは、電気自動車などにも使われている実績のあるバッテリーです。最大のメリットはエネルギー密度が高いこと。つまり、同じ容量でもより軽く、コンパクトに作れます。持ち運びやすさを重視するなら、大きなアドバンテージです。サイクル寿命は500回から1,000回程度のものが多く、リン酸鉄には劣りますが、週末に使う程度なら十分な性能と言えます。どちらが良い悪いというよりは、何を重視するか、という話なんですよね。毎日ガンガン使いたい、防災用に長期間安心して備えたいなら「リン酸鉄」。少しでも軽く、コンパクトなモデルが欲しいなら「三元系」。あなたの使い方に合った心臓部を選んであげてください。
最も差がつく「保管方法」長期不在時の最適解とは
どんなに高性能なバッテリーを搭載したモデルでも、保管方法を間違えれば、その寿命はあっという間に尽きてしまいます。特に、たまにしか使わないという人ほど、この保管方法が重要になります。
まず、長期保管時の充電残量。これは絶対に覚えておいてほしいのですが、100%の満充電や0%の空っぽの状態で長期間放置するのは、バッテリーにとって最悪の仕打ちです。満充電状態はバッテリー内部の電圧が高い状態が続き、劣化を早めます。逆に0%の状態が続くと、バッテリーが深くまで放電しすぎて二度と充電できなくなる「過放電」という状態に陥るリスクがあります。
じゃあ、どのくらいがいいのか?多くのメーカーが推奨しているのは「50%〜80%」の範囲です。個人的には、間を取って60%前後で保管するのが一番安心じゃないかと思います。数ヶ月に一度は状態を確認し、減っていたら60%前後まで充電してあげる。この一手間が、数年後のバッテリー寿命に大きな差を生むのです。
そして、もう一つは保管場所の温度。これも「熱」の話に繋がりますが、バッテリーは極端な高温も低温も苦手です。最適なのは、人間が快適だと感じる20℃前後の常温環境。押し入れやクローゼットの奥などが良いでしょう。絶対にやってはいけないのが、夏場の車内や物置、直射日光の当たる場所での保管です。面倒くさがらずに、家の中の涼しい場所に保管してあげてください。
充放電サイクルの誤解「0-100%」は避けるべき?
バッテリーの寿命の指標として「サイクル回数」という言葉がよく出てきます。例えば「サイクル寿命3,000回」とあれば、0%から100%までの充放電を3,000回繰り返しても、初期の80%程度の容量を維持できますよ、という意味です。
ここで一つ、面白い事実があります。実は、毎回0%まで使い切って100%まで充電する、という使い方よりも、例えば20%から80%の間でこまめに充放電する方が、バッテリーへの負荷は少ないのです。0%付近の過放電領域と、100%付近の過充電領域は、バッテリーにとって最もストレスがかかる領域だからです。
「え、じゃあ毎回残量を気にしなきゃいけないの?面倒くさい!」って思いますよね。でも、安心してください。現代のポータブル電源には、BMS(バッテリーマネジメントシステム)という非常に賢い頭脳が搭載されています。このBMSが、過充電や過放電を防ぎ、セルごとの電圧を均一に保ち、温度を監視するなど、バッテリーを常に最適な状態に保つよう見張ってくれているのです。
ですから、ユーザーが神経質に残量をコントロールする必要はほとんどありません。BMSが、私たちが気づかないところで、寿命を延ばすための仕事をしてくれているのです。ただ、BMSの性能はメーカーやモデルによって差があります。信頼できるメーカーの製品を選ぶことが、結局はバッテリーを長持ちさせるための近道、というわけですね。
まとめ ポータブル電源のパススルーと寿命の真実

さて、ポータブル電源のパススルー機能と寿命について、かなり深く掘り下げてきましたが、いかがだったでしょうか。「パススルーは寿命を縮める」という言葉は、半分本当で半分はもう過去の話になりつつある、ということがお分かりいただけたかと思います。
重要なのは、パススルーには「バッテリー経由型」と「バイパス型」があり、寿命への影響を本気で考えるなら「バイパス型」、あるいはUPS機能を搭載したモデルを選ぶのが賢明だということです。そして、その便利な機能を支えるのは、バッテリーの天敵である「熱」をいかにコントロールするか、という視点です。風通しの良い涼しい場所で使う、ファンの邪魔をしない、といった基本的な配慮が、何よりも大切なのです。
さらに、寿命を決定づけるのはパススルー機能だけではありません。心臓部であるバッテリーが長寿命な「リン酸鉄リチウムイオン」なのか、それともコンパクトな「三元系」なのか。長期保管する際に60%前後の残量を保ち、涼しい場所に置いているか。こうした日々の付き合い方こそが、あなたのポータブル電源が10年後も頼れる相棒でいられるかの分かれ道になります。
結局のところ、一番大切なのは「自分の使い方に合った一台を、正しく理解して選ぶこと」に尽きます。この記事が、あなたが漠然とした不安から解放され、自信を持って最高のポータブル電源を選ぶための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。